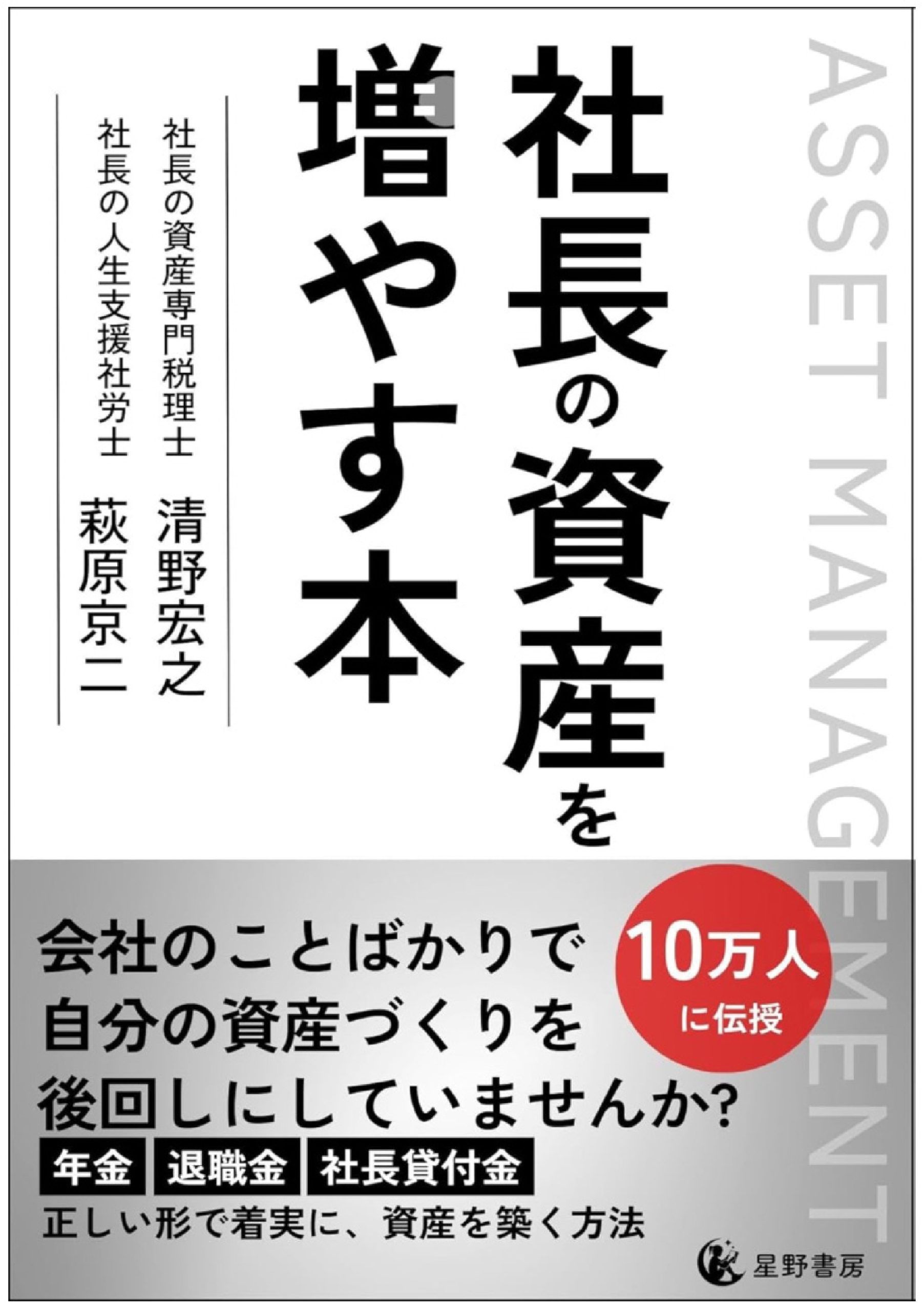■役員退職金は3つの基準を満たす必要がある
役員退職金の損金算入可否は、とても大きな問題です。
この退職金に関して、税務署は次の3つの基準から、
判断していると言われています。
1.金額が過大かどうか(金額基準)
2.正当な手続きを経ているか(形式基準)
3.退職の事実があるか(実質基準)
今回は、この3つの基準のひとつ目、
「金額基準」についてポイントをお話しします。

■【金額基準】税理士でも100%の確証を持てないこともある
基本的に、役員退職金は法律で定められた制度ではないため、
法人が支払い可能であれば、支給額に上限はありません。
税法上では、「過剰に高額な部分」は「役員賞与」の扱いとみなされ、
損金として計上することはできないのです。
一般的には、最終報酬月額方式(最終報酬月額×勤続年数×功績倍率)で計算することで、
役員退職慰労金が税務上で損金として認められやすいと言われています。
ただし、これはあくまでも目安であり、
かならずしも100%損金として扱われるわけではないことに注意してください。
さらに、役員退職金の規程を本格的につくる方法もあります。
たとえば、
「1年あたりの平均額(類似法人の役員在任1年あたりの役員退職金の平均額)などを勘案して、
最終報酬月額を150万円とする」ことも選択肢のひとつになります。
繰り返しお伝えしますが、税務上はこれでOKという保証はありません。
「役員退職金規程があれば、どんな金額設定でも大丈夫」
と思っている人もいますが、そんなことはありません。
ただし、合理的な支給基準が存在するほうが有益であることは、
間違いないと言えます。
役員退職金の規程があることで、
税務署に対して「このような基準で支給しています」
と根拠を示すことができるからです。
ただ、損金の計上が100%保証されるわけではないことに、
注意する必要があります。
税務上、退職金の適正な金額はいくらなのかを一概に言及することは難しく、
税理士でさえ100%の確証を持てていないのです。
「社長の退職金には税務上のリスクが存在し、絶対に大丈夫だと言える基準はない」
ことを知っておきましょう。

『社長の資産を増やす本』(星野書房)
好評発売中!