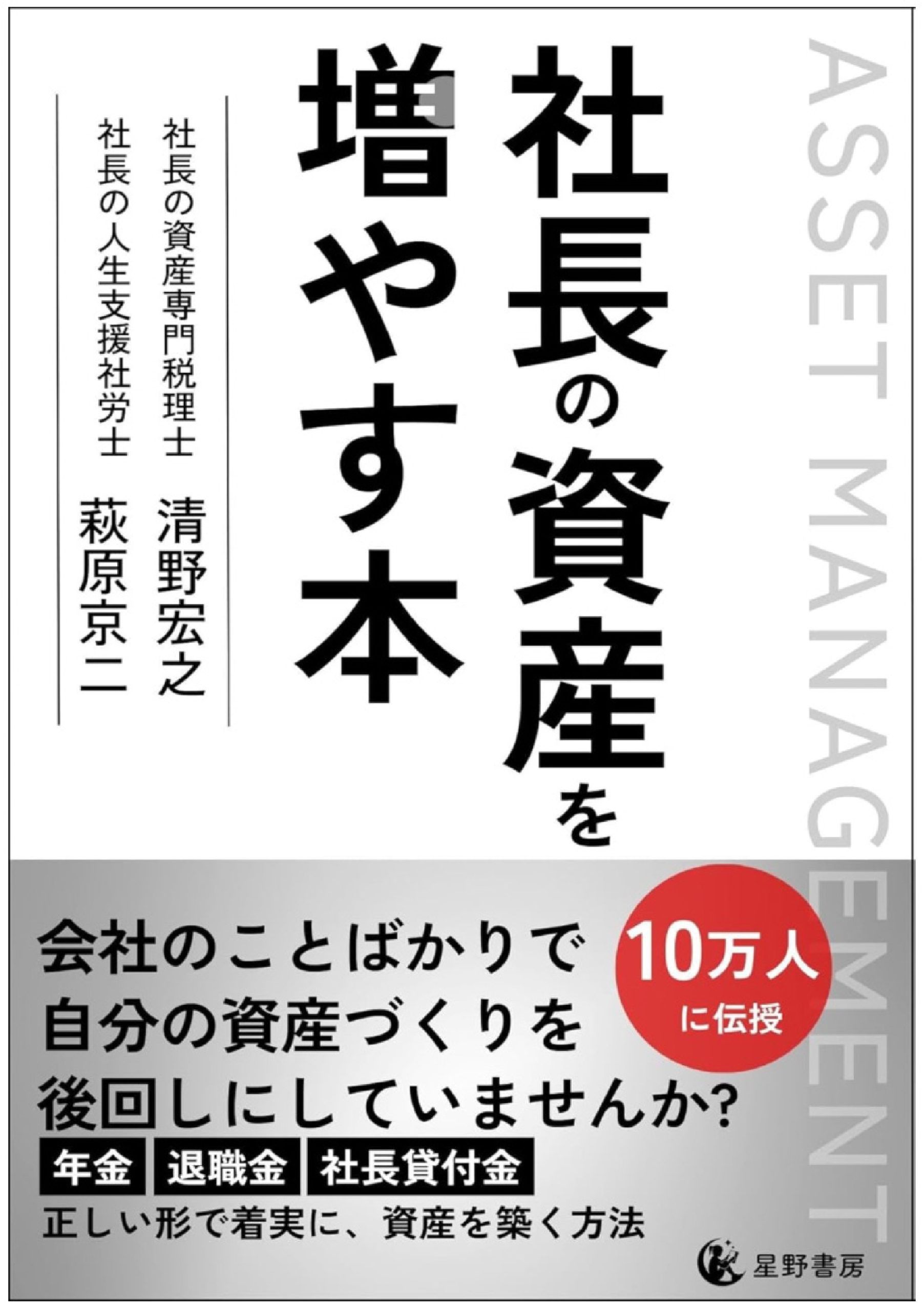■専門家のアドバイスを受けるには希望の金額を明確にする
役員退職金が税務署により損金として認められるかどうかは、
これまでのブログでもお伝えしたように、3つの基準から判断されます。
でも、税務署の判断が一律であるとは限りません。
どのような対応をしても、こうすれば絶対に大丈夫と、
リスクが完全に取り除かれるわけではなく、
どんな場合でもリスクは残ります。
大切なのは、社長自身がどれくらいの金額を望んでいるのか、
また、その際にどの程度のリスクを許容できるのかを、
ある程度自分で決めることです。
そうでなければ、専門家は適正なアドバイスもできません。
まずは、「どのくらいの金額がほしいのか」を明確にすることで、
専門家からアドバイスを受けることができます。
むしろ、「どうしたい」と自分の意思表示をしなければ、
たとえ専門家であっても手の打ちようがないのです。
退職金として望む金額を決定するには、
以前ブログでもお伝えした
「ライフプラン」や「ファイナンシャルプラン」を
考慮する必要があります。
具体的な計画がなくては、
適切な金額を決めるのは難しいでしょう。
「できる限りたくさんもらいたい」
と思うのは自然なことですが、
それだけの金額がほしい理由を考えなければ、
本当の意味での満足感を得られないはずです。
-scaled.jpg)
■会社の視点を持って退職金を決定する
役員退職金を受け取る際には、当然ながら、
会社からの目線を持つことが不可欠です。
つまり、会社が社長のほしい金額を支払えるだけの
財務状態にあるかどうかを確認する視点を、
欠かすわけにはいきません。
役員退職金を支払ったことが原因で、
会社の財政状態が揺らいでしまっては本末転倒です。
株主総会や取締役会での決議前に、
社長がほしい金額と会社が実際に支払える金額の両面を考慮して、
決めていく必要があります。
退職金を何のために使うのか、いくら必要なのか、
その原資は会社にあるか、
もしない場合はどのように準備するのかを
しっかり考えておきましょう。
たとえば、次のようなことを考慮することで、
必要な役員退職金の金額が明確になります。
・退職後に自身がやりたいことを行うために
必要なお金は、どれくらいか?
・退職後に一生涯受け取れる老齢年金以外に
必要な生活資金は、月額いくら?
・遺族の相続税を支払うために準備すべき資金は、
いくら必要か?
・後継者以外の相続人への遺産分割資金として、
どのくらいの資金が必要か?
・会社や自身の経営理念や想いを後継者に託し、
会社を発展させるには、内部留保として
いくら会社に残しておきたいか?
といった計算から、
本当に必要な役員退職金額が見えてくるのです。
-scaled.jpg)
『社長の資産を増やす本』(星野書房)
好評発売中!