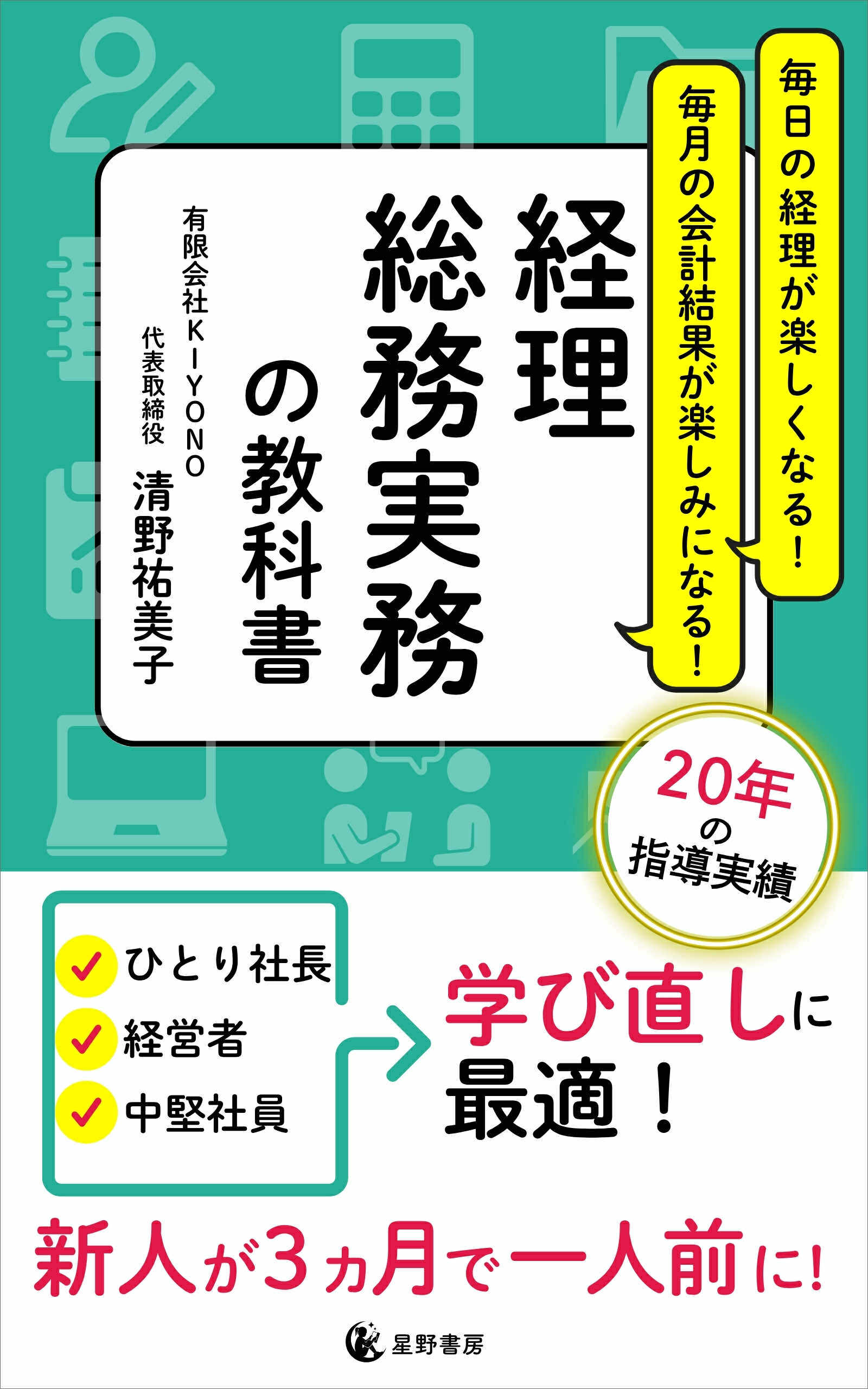◼️組織図を作成して会社の基盤を築く
個人事業主として活動を始め、
その後「ひとり社長」として会社を設立するケースは珍しくありません。
では、その際に最初に整えておくべき資料は何でしょうか。
まず取り組みたいのは、「組織図」と「社員名簿」の作成です。
とくに組織図を用意することは、
中小企業にとって重要なプロセスといえます。
会社の構造を図で示すと、
社員は自分の立ち位置や役割を理解しやすくなり、
組織全体のしくみを把握する助けとなるのです。
そして、組織図をつくることで、
従業員一人ひとりの担当業務や責任範囲が明確になり、
社内のコミュニケーションが円滑になります。
その結果、業務全体の効率化にもつながります。
会社を立ち上げたばかりの「ひとり社長」の段階では、
組織図には当然「代表取締役」だけが記されるシンプルな形になります。
そして、人が増えて役割を分担する必要が出てきたときには、
第2段階、第3段階へと組織図を拡張していくといいでしょう。
企業は一気に大きくなるものではありません。
一般的には、まず社長の下に直接指示する役員を配置し、
その下に担当者を置き、
さらにその下に数名のスタッフを加える、
といった形で少しずつ組織を整えていくのが通常です。
スタッフの数が増えてきた段階では、
組織図には全員を記載しておくことをおすすめします。
-scaled.jpg)
◼️社員名簿を活用して調査に対応する
社員名簿とは、企業が従業員を雇用する際に
かならず作成・管理しなければならない書類であり、
労働基準法で定められた「法定三帳簿」のひとつにあたります。
この法定三帳簿には、
「労働者(社員)名簿」「賃金台帳」「出勤簿」
の3種類が含まれています。
社員名簿の作成自体は義務づけられていますが、
役所などに提出する必要はありません。
ただし、労働基準監督署の監査や税務調査では、
最初に確認される重要な書類のひとつです。
作成していないことが判明すれば、
ペナルティを受ける可能性もあるので注意しましょう。
会社の代表や役員は、
法律上は労働者には含まれないため、
本来は社員名簿の対象外です。
ただ、社会保険制度では役員も被保険者にあたるため、
社会保険事務所の調査を見据えて
名簿に記載しておくことをおすすめします。
社員名簿を作成する際は、
Excelやスプレッドシートといったツールを使うのが便利です。
決まった様式はなく、
法律で定められた必須項目さえ盛り込まれていれば、
形式は自由で問題ありません。
◼️社員名簿を最新情報に更新して従業員を把握する
社員名簿(労働者名簿)に記載する内容には、
労働基準法で義務づけられた「必須項目」と、
会社が独自に加えることができる「任意項目」があります。
必須項目として定められているのは、
氏名、生年月日、性別、住所、職歴、従事する業務の種類、
雇入れ年月日、退職(または死亡)年月日とその事由です。
一方で任意項目としては、
社員番号、役職、所属部署、連絡先、緊急連絡先、
家族構成、保有資格などがあります。
マイナンバーは、
社員名簿に直接記載する項目としては適切ではありません。
その理由は、社員名簿がマイナンバーの利用目的以外でも
参照される可能性があるからです。
そのため、社員名簿にはマイナンバーを記入せず、
該当欄には「別途保管」と明記し、
存在を示すにとどめておきましょう。
実際の番号を記載することは、絶対に避けてくださいね。
社員名簿は、労働基準法施行規則により、
5年間の保存が義務づけられています。
その起算日は入社日や名簿作成日ではなく、
退職・解雇・死亡のいずれかの日となります。
ここは誤解しやすいポイントなので、注意が必要です。
また、社員名簿は法律で作成と保管が定められているだけでなく、
自社の従業員情報を正確に把握するうえでも欠かせません。
常に最新の内容に更新し、管理しておくことが大切です。
組織図と社員名簿を整えておくことは、
あなたの会社が未来へ進むための力強い第一歩になりますよ。
-scaled.jpg)
『毎日の経理が楽しくなる!
毎月の会計が楽しみになる!
経理・総務実務の教科書』
好評発売中!